こんにちは、あらおです。
今回は久々に趣向を変えて、最近読んだ経済本のお話です。
河野龍太郎『日本経済の死角』です。けっこう売れてるみたいなので読んだ方もいるかもしれません。
本書は、主に日本の失われた30年にフォーカスし、日本経済の活力が失われた要因について分析しています。
多くのデータをベースにして議論しているため説得力があり、失われた30年に対する新たな見方を提供しています。
投資やFIREの観点から、特に本書で特に興味深かったのは以下の2点です。
- 生産性と実質賃金には相関性がない
- ほとんどのイノベーションは格差を拡大させる
以下、順にみていきます。
生産性と実質賃金には相関性がない
まず、本書最大の売りといえる主張が「生産性と実質賃金には相関性がない(日本は)」点です。
詳細は本書を確認いただきたいですが、例えば、以下の点が指摘されています。
- 1998~2023年で日本の生産性は30%上昇しているが、実質賃金は±0~ややマイナス
- 同時期、ドイツ・フランスの生産性上昇率は日本より低いにも関わらず、実質賃金は約20%上昇
これはなかなか刺激的なデータですよね。
「日本人はただ労働時間が長いだけで効率的に働かないから(生産性が低いから)、給料が上がらないんだ」みたいな論調がずっと続いていたと思います。
私も概ねその通りなんだろうと漠然と思っていましたが、それを真っ向から否定するデータです。
日本だけ生産性と実質賃金に相関性がない理由として、本書では主に大企業が内部留保を貯めこみ過ぎている点を指摘しています。
そして大企業が貯めこむ要因として、例えば、以下が挙げられています。
- 過剰な財務健全化(メインバンク制の崩壊)
- 給料を上げない⇔内需縮小の負のスパイラル
- 定期昇給(個人ベースの給料アップ)による錯覚
- 安価な労働力の供給(女性、高齢者、移民)
日本は大企業の正社員であれば定期昇給で満足感があるため、これを守るための(物価上昇と同程度の)ベースアップは考えられるが、インフレを上回るほどのベースアップを実行するインセンティブが、様々な要因から働かないという主張だと捉えました。
大企業が物価上昇程度のベースアップ(実質賃金±0)なら、中小企業社員や派遣労働者はインフレに負けて実質賃金マイナスになるのが濃厚です。
以上から、日本の労働者は既に十分がんばっているが、それが給料に跳ね返るかは大企業次第であり、かつ現状労働者に報いるインセンティブが働かない状況である、というところかと思いました。
この点、政治が少しずつ改善を探り始めている状況にも思えますが、正直上手くいくかは不明であり、仮に上手くいくとしても相当の時間を要する問題だと考えています。
だとすればこの傾向はしばらく継続すると考えるのが自然で、個人の対策としては、月並みですがやはり大企業に投資することになると思います。
今起こっているのは、労働者が得るべき所得が大企業に移転し続けているという現象であり、その影響もあっての好業績連発・株高となってますので。
ほとんどのイノベーションは格差を拡大させる
「ほとんどのイノベーションは格差を拡大させる」というのも、個人的に特に印象的な視点でした。
正確には、イノベーションには、自動化等により実質賃金の下押し圧力となる収奪的なイノベーションと、それ以上に新たな労働需要を創出して実質賃金の押し上げ圧力となる包摂的なイノベーションがあるとのこと。
そして重要なのは、歴史上、包摂的なイノベーションは下記2つしかない点。
- 19世紀後半:蒸気機関車網の整備
- 主に戦後:モータリゼーション(自動車の普及)
いずれも輸送技術なのが興味深いですね。商品・人の輸送が容易になり、新たな需要・新たな雇用の創出に貢献しました。
逆に言えば、産業革命も、IT革命も、はるか昔の農耕の発明でさえも、基本的には格差を拡大させる収奪的なイノベーションでした。
ここ最近のAI革命も残念ながら収奪的イノベーションの要素が強そうですね。
これらの技術は、たしかに消費者や社会全体としての利便性を向上させるものですが、労働者の実質賃金を減少させる性質もありました。
上記の説から言えるのは、資本主義+技術革新という組み合わせは本質的に格差拡大装置であり、放置すれば格差は広がり続けるのが原則という事実です。
そして、運よく包摂的なイノベーションが登場した時にのみ労働需要が高まり、分厚い中間層が発生する豊かな時代が到来する、という解釈もできるかと思います。つまり、こちらが例外。
このことから、日本の戦後はモータリゼーション+人口ボーナスという稀に見る好条件が重なった超幸運な時代だったとも考えられます。
今の世代は戦後~失われた30年しか知らないので、高度成長期・バブル期こそ日本の基準とすべき所と考えがちな傾向がありますが、好条件を割り引いて考える必要があるかもしれませんね。
失われた30年というより、「普通の条件なら日本はこんなもんの30年」という見方もできるかと。
(個人的に日本の復活を願う心意気は持ちつつ…なんですが。)
ともかく、高度成長期・バブル期は例外的な時代という見方はあると思います。
それゆえ、例えば「良い大学に入り、良い会社に入る」等の、この時代を前提とした常識が現代では通用しなくなるという心構えは持ってもよいかと思いました。
まとめ
以上、『日本経済の死角』についてでした。
色々書き散らしてしまいましたが、上記は本書を読んでの私の感想です。
失われた30年について、いくつかの新たな視点を得られました。
本書の内容についてはぜひご自身でご確認ください。
というわけで、普段は本格的な経済書は普段あまり読むほうではありませんが、なかなか面白かったです。
これらのやや学術的な知識も仕込んでおけば、市場の流れを解釈する力も一段と深まるような気がしています。
なので、今後はたまにこういった知識も取り入れていきたいと思った次第でした。
X(旧Twitter)もやってます。
人気ブログランキングに参加しています。
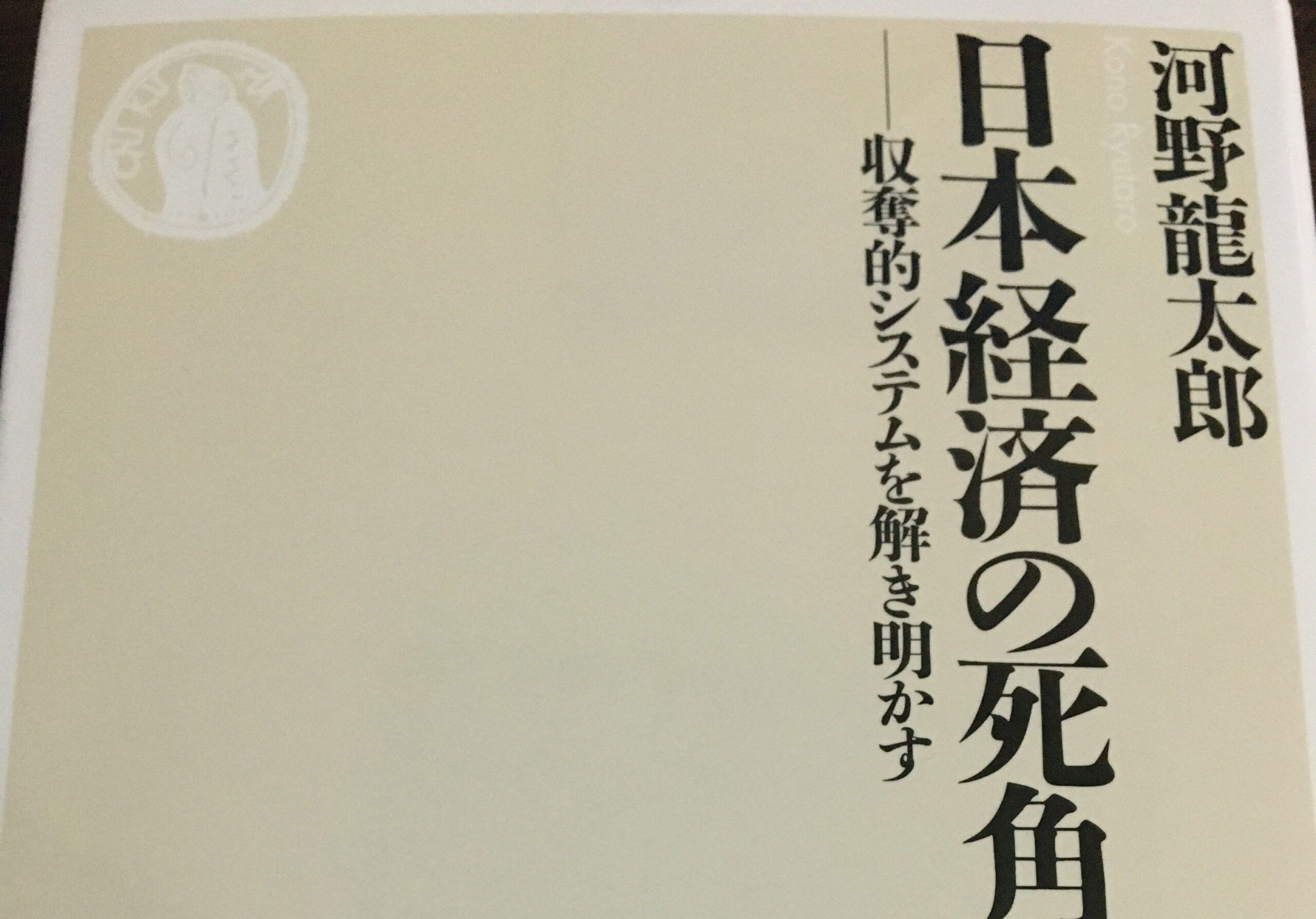


コメント